top of page


山北を知る・学ぶ
山北の歴史は古く、今から5千年前、縄文時代中期頃の尾崎遺跡や共和小学校遺跡が見つかっています。
弥生時代、古墳時代の遺跡や遺構も残っており、縄文時代中期から現代まで様々な人々が生活を営んでいたことがわかっています。 平安時代末期には、秀郷流藤原氏である波多野遠義の子・秀高が河村氏を名乗り、河村城を居城に山北を統治します。このころの山北は「川村(河村)郷」と呼ばれていました。
戦国時代になると、河村城は小田原北条氏の持城となり、河村新城・中川城・湯ノ沢城とともに山梨を拠点とする武田氏に備える重要な役割を果たしたのです。
戦国時代が終わり、江戸時代になると山北は小田原藩に属します。元禄の大地震や宝永の富士山噴火など大きな災害に襲われた山北は一時、幕府領になるほどの大被害を被ります。富士山に近い山北では、宝永大噴火により大量の火山灰が降灰し、それが原因で皆瀬川は氾濫を繰り返すようになります。 その洪水対策とその後の水不足によって、山北の人々は川入堰、瀬戸堰などの用水建設に力を注ぎます。この時、建設された用水は、今でも大切な水を供給しています。
近代の山北は明治22年の東海道線開通によって大きく発展し、太平洋戦争の際は、山北も戦火に巻き込まれることとなります。 長い歴史の中で、山北には多くの貴重な歴史の痕跡と現在に伝わる民俗文化が残されています。その貴重な遺産を多くの方に伝えてゆく一助なるようにまとめたものです。
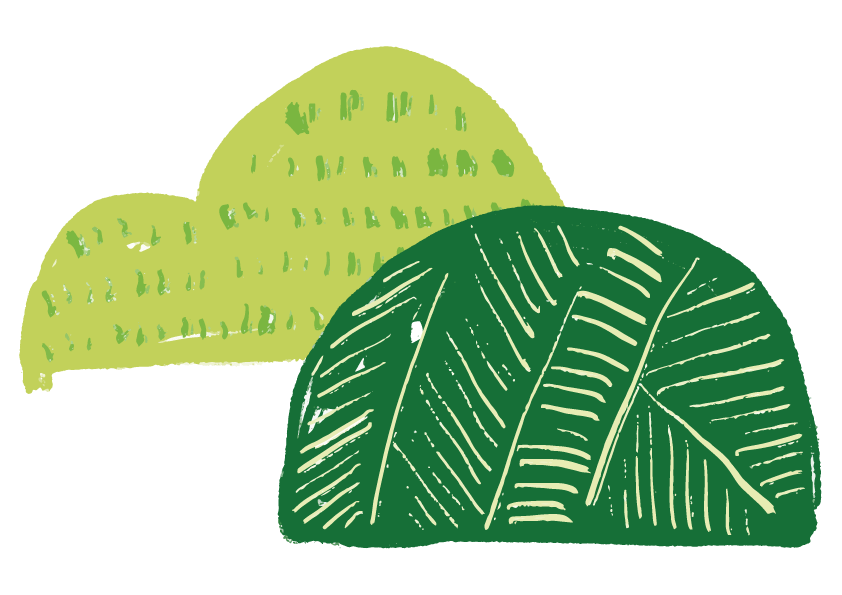

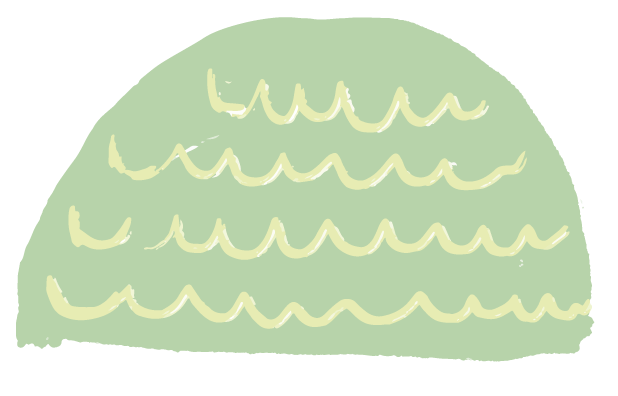
パネルで
取り上げる資源
河村城跡

山北駅の南側、山北・岸地区にある城山と呼ばれる浅間山頂上にある城跡。自然の地形を活かした中世の山城です。
北の旧皆瀬川、南の酒匂川に囲まれた標高225mの山の地形を利用して築城されています。
河村城は、山北地域を治めていた河村氏が築城したと言われおり、室町時代の始め(南北朝時代)、河村城と書いてある記録が最も古いもので、このころにはお城があったと考えられています。
現在見られる城跡は戦国時代に北条氏の城だったころの姿です。
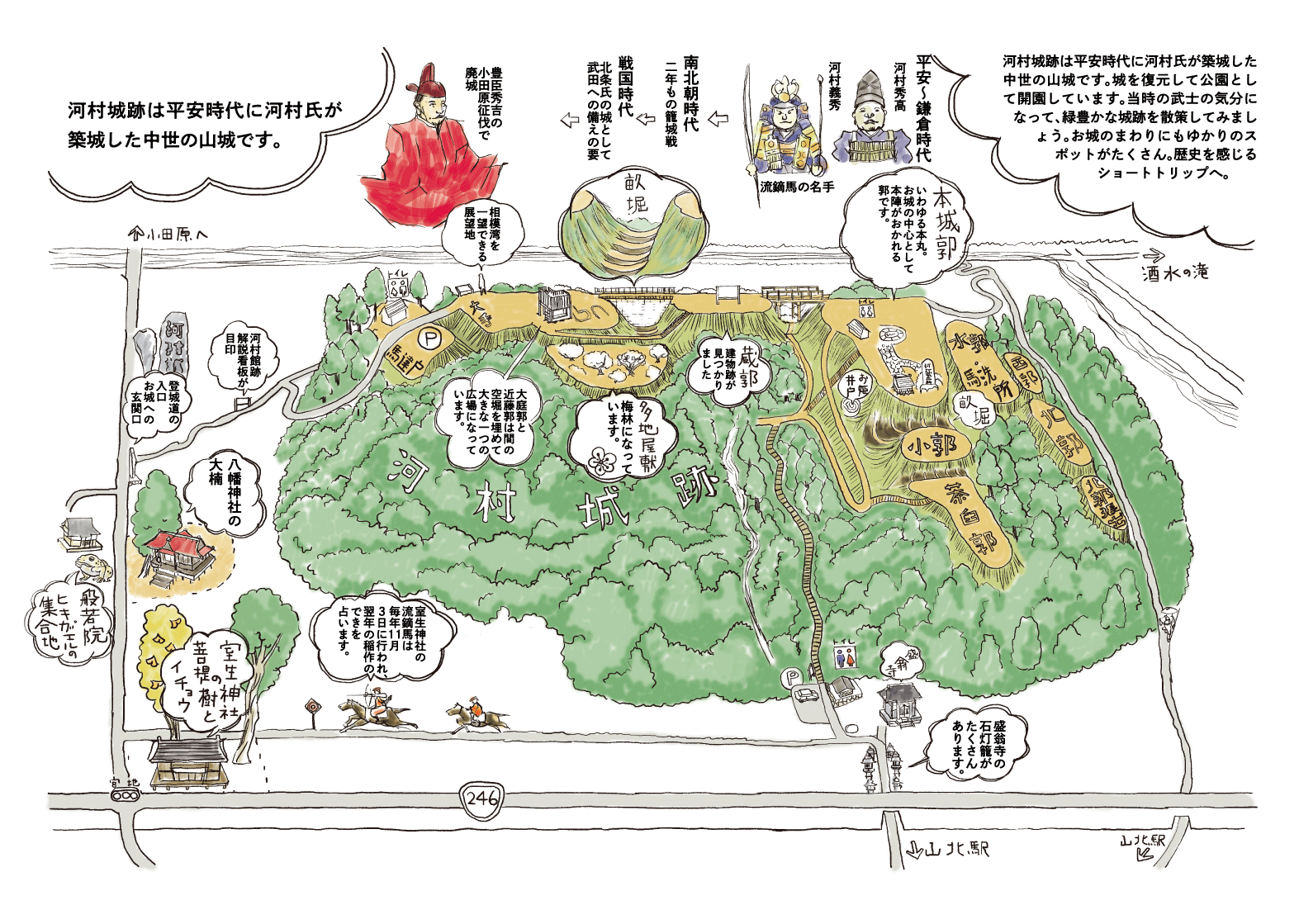
障子堀(畝堀)
障子堀は堀を縦横のマスの様に掘ることで、攻め入った敵が細い土手の上を進むしかなくなって自由に動けなくなるもので、北条氏の山城によく見られます。
河村城跡には、神奈川県内最大の障子堀が残ってます。

般若院とヒキガエルの集合地

般若院は、河村初代、河村秀高以来の菩提寺です。元々は河村城の大手、湯坂の地にありましたが、文明年間に僧侶・日円が現在地の北側に移転しました。
戦国時代には、戦火で炎上、江戸時代にも災火で炎上し、現在地に移転しました。
また、この場所は、神奈川県指定天然記念物の「山北町岸のヒキガエル集合地」として登録されています。 この地域はヒキガエルが多産することで有名で、「蛙合戦」として新編相模国風土記稿にも取り上げられています。
毎年3月上旬から下旬にかけて多くのヒキガエルが池に集まり産卵します。やがて、生まれたヒキガエルが6月頃山に帰ってゆきます。
般若院の境内にはヒキガエルの石像があります。
bottom of page