


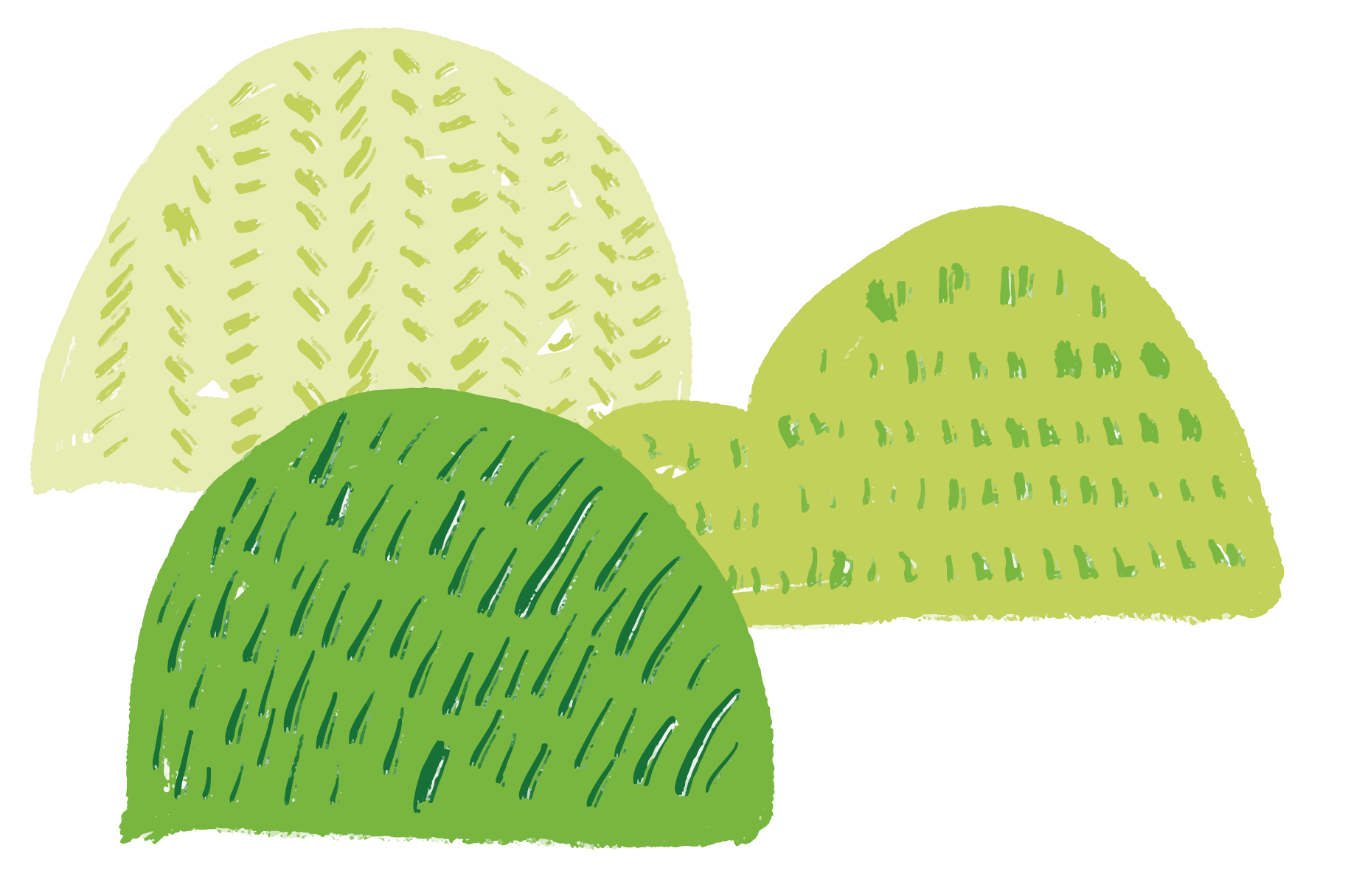
山北の祭り
室生神社の流鏑馬
県指定無形民俗文化財/平成7年2月14日指定
室生神社の流鏑馬
毎年11月3日の室生神社の例大祭で行われる流鏑馬。 神社前の馬場、鳥居の前を使って、馬を走らせながら馬上から射手が三つの的を順番に射貫いてゆき、翌年の稲作の出来を占う神事です。
流鏑馬のはじまり「河村義秀」
室生神社の流鏑馬のはじまりは吾妻鏡にも描かれた「河村義秀の逸話」によるとされています。 河村義秀は、相模国河村郷の武将です。源頼朝が平氏の治める伊豆を攻めた、知承4年(1180年)石橋山の戦いの際、平氏方として戦いました。 その後、建久元年(1190年)の鎌倉鶴岡八幡宮の流鏑馬時に射手が一人けがをしたため、急遽代役が必要になりました。その代役に選ばれたのが鎌倉幕府より死罪を言い渡されていた河村義秀でした。義秀は大変、弓矢の腕が立つ武将だったので、的を無事に射貫き、源頼朝からゆるされたのです。 河村郷の領地を戻された建久元年(1190年)の翌年から室生神社の流鏑馬が始まったすると800年余続いている神事なのです。
01.馬場駈け/神社前馬場
騎乗者がハッピ姿で裸馬に乗り、2頭で馬場を一往復走ります。1頭は先導役でもう1頭に射手が騎乗します。多くの流鏑馬の神事では専門家が騎乗しますが、山北では騎乗者を室生神社の氏子が努めます。
04.垢離取りの儀/垢離取場
垢離取場は旧皆瀬川の岸辺で山北町山北字金森にあります。そこで「垢離取りの儀」を行います。「垢離取りの儀」は騎馬を清める儀式です。垢離取場の中央に御幣が祀られ、その周りを騎馬が3周したのち足と口を清めます。
02.流鏑馬開始の式
/神社拝殿前
騎乗者が正装に着替え、お祓いをうけます。山北の流鏑馬の正装は橙色の水干と兜をかぶります。
05.流鏑馬始式/神社鳥居前
一の的を鳥居前の馬場中央に社殿を向けて立て、騎馬に騎乗し、一の的の周りを3周したあと、騎射し流鏑馬が始まります。
一の的の先には先導する先馬が待っており、馬場尻のほうへ走りだすと射手の騎馬が後続し、二の的、三の的を順に射貫きます。ここまでを神事として形式的に行います。 その後、「騎射」となり、先導馬と射手が交代しながら4回騎射し、的にあたった数が多いほど、翌年豊作になるといわれています。
03.馬場入りの儀
/神社前馬場
流鏑馬神事関係者が行列を組み、馬場に入場します。先頭を室生神社の神主がつとめ、お祓いをしながら行列し、垢離取場へと向かいます。
山北のお峯入り
国指定重要無形民俗文化財 昭和56年1月21日指定
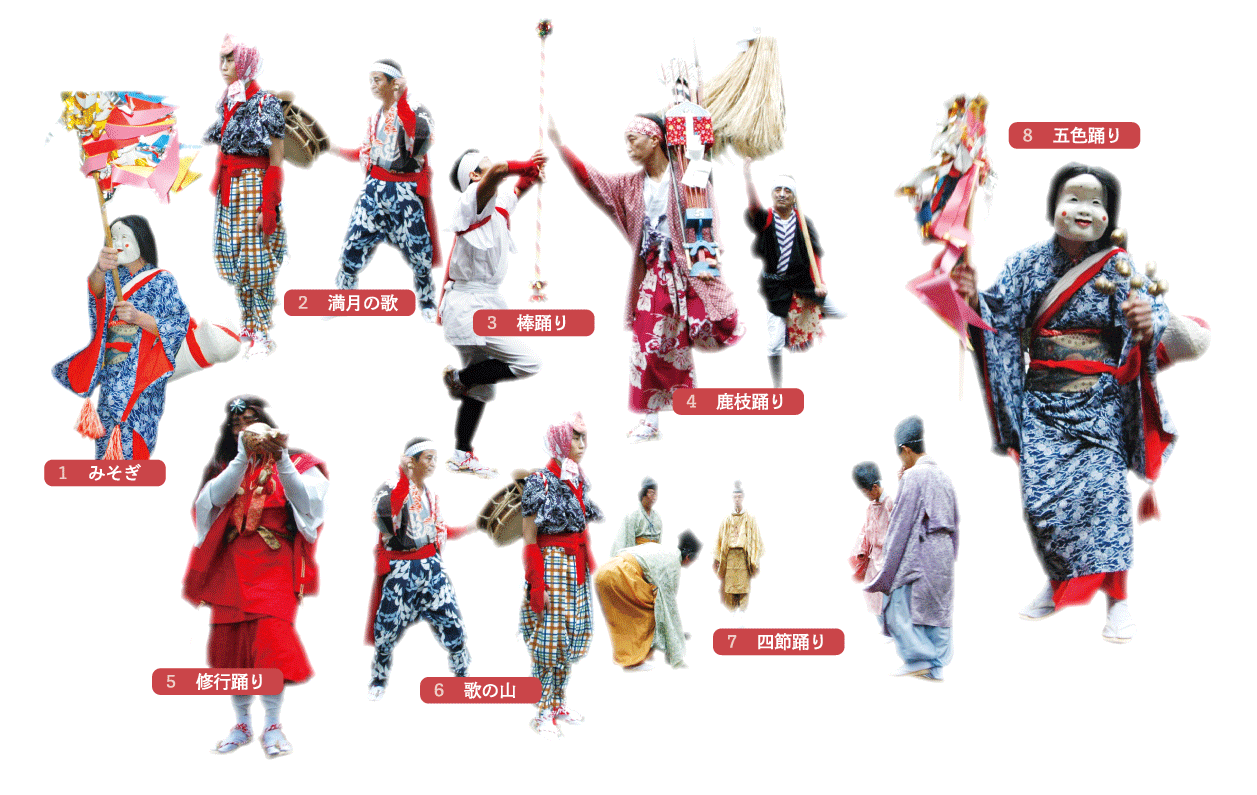
修験道を今に伝える
山北町共和地区に古くから伝わる民俗芸能。 「お峯入り」とは山中で修業を行うことを意味し、修験道の儀礼が芸能化したものと考えられています。また、南北朝時代に宗良親王が河村城に難を逃れた時から始まったという伝承もあり、笛・太鼓の調べや歌詞は万葉の時代を感じさせます。 演技は8種類11演目あり、天狗、獅子、おかめ、山伏、太鼓、笛などの役を約80名の男性が演じます。歌や踊りはすべて口伝えで伝承されていて、近年では5年ごとに公演を行っています。 なお、現在のお峯入りは昭和9年(1934)に40年ぶりに復活させ、古い衣装道具を見本に新しく整え伝承されてきたものです。史料で確認できる最も古い行事の記録は文久3年(1863)8月16日にさかのぼります。

世附の百万遍念仏
県指定無形民俗文化財 昭和53年6月23日指定
生まれ変わりをねがう念仏
約600年前の南北朝時代、後醍醐天皇が京都の都から落ち延び、ここ山北町の世附で亡くなったという伝承から始まったと伝えられる念仏信仰です。 百万遍念仏とは、仏様の名前を百万回唱えると、願いがかなうといわれる信仰です。 毎年2月15日から17日まで山北町世附の能安寺で行われていましたが、三保ダムの建設に伴い、現在では山北町向原に移転された能安寺で毎年2月中旬の土曜日・日曜日に行われています。

世附の百万遍念仏
世附の百万遍念仏は、大数珠を巨大な滑車につけ数珠を回転させるという、全国でも珍しい念仏です。 数珠は「水桃木」というサルナシやフジで作られ、長さが9メートルにもなります。長老が「数取り」という役を行い、数珠の回転を数えます。 念仏の声には平音、中音、高音の3音階あり、指揮者の指揮で念仏の音程を変化させます。 日曜日の最後は「カガリ」と呼ばれる融通念仏が行われます。道場の中央に置かれた太鼓を囲み念仏を唱えます。 道場の天井には山から刈り取ってきたスゲ草で縄を作り、赤・白・青・黄・黒の5色の小さい幣を吊り下げ、しめ飾りを天井いっぱいにはります。融通念仏が終わるとこのしめ飾りを取り、家の戸口にかけると厄病除けになるといわれています。
獅子舞と遊び神楽
念仏が終わると獅子舞が始まります。もともとは百万遍念仏とは関係がありませんでした。江戸時代の終わり頃に伊豆か甲州(山梨)から伝わった獅子舞を、百万遍念仏の時に同時に行うようになっていったようです。
01.剣の舞
獅子一人が剣と鈴を持って舞います。道場を清めるために舞うといわれています。
04.二上がりの舞
「ヒョットコメン」を付けて舞います。天の岩戸開きの時の舞で世の中を和やかにする舞といわれています。
07.鳥さしの舞
日本三大仇討ちの一つ、曽我兄弟が鳥さしに身を変じ、親の敵を討つまでの苦心を物語る舞といわれていま�す。
02.幣の舞
獅子1人が幣と鈴を持って舞います。悪魔祓いをして世を浄める舞といわれています。
05.おかめの舞
「おかめ」に扮して舞います。「二上がりの舞」と同じく世の中を和やかにする舞といわれています。
03.狂いの舞
獅子に二人が入り舞います。神が自ら悪魔(獅子)に変じて、悪魔を引き寄せ、これを全部退散させる舞といわれています。
06.姫の舞
獅子に二人が入り舞います。「カザリハ」ともいわれ、諸事の霊を慰める舞といわれています。
白籏神社の祭囃子
町指定無形文化財 平成16年11月25日指定
神奈川県の西部の祭囃子
白籏神社例大祭(4月第1週の日曜)に行われるお囃子。 いいつたえによれば、神奈川県西部に多くみられる江戸祭囃子ではないお囃子だそうで、大変貴重なお囃子だと考えられています。 曲目は江戸祭囃子より多く8曲あり、連行(お��祭りの行列)の場面によって曲が変わるのが特徴です。
01.いぶれ(湯触れ)
神輿が出発の時は拝殿から鳥居まで、帰着のときは鳥居から拝殿まで使う曲。
04.昇殿. 05.追廻し囃子
休憩中に交互に演奏する曲です。
02.京囃子 03.上総囃子
神社をでてからの御幸のときに交互に演奏します。
06.おんがく囃子
神輿が神社に戻る際、上り坂を進みます。その時に奏でられる曲で「どっこいどっこい」の掛け声とともに神輿を押し上げます。
その後は、鳥居をくぐると①「いぶれ」で拝殿まで進み、拝殿の周りを④「宮神楽」とともににぎやかに3周まわります。最後に神輿の上の鳳凰飾りを外し、社殿におさめるときに⑧「みあがり(宮上がり)」を演奏します。
04.宮神楽
神輿が休憩場所で到着前に一段とにぎやかに奏でる曲。
川村囃子
町指定無形文化財 ��昭和50年7月17日指定
江戸時代から続く川村囃子
川村囃子は、山北と岸で行われる祭囃子です。 山北では、室生神社例大祭(11月3日)と道祖神祭り(1月中旬)で行われます。岸では八幡神社例大祭(4月第1週の日曜)で行われます。 川村囃子のはじまりは江戸時代なかごろ、小田原の多古(旧足柄村)にある白山神社の祭囃子として江戸祭囃子を取り入れた小田原囃子が伝わったと考えられています。
